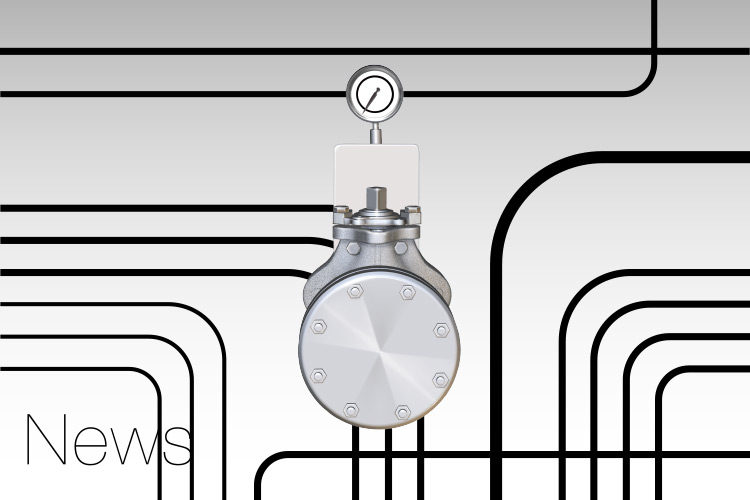「タンクの付随作業が増えるほど、安全対策の強化が必要」
「老朽化対策をはじめ長期的な備えを」日本タンクターミナル協会
小幡柾夫会長

タンクターミナルは陸・海を結ぶ液体バルク貨物のサプライチェーンの結節点として、タンク保管のみならず多様なニーズへの対応が求められるようになった。物流業界の他業種に比べて新規参入のハードルが高く、タンクターミナル各社はそれぞれの生い立ちや立地、取扱い貨物などの「持ち味」を生かし、各社のオリジナリティーに新しいニーズを取り込み、堅調な成長を続けている。日本タンクターミナル協会(JTTA)の小幡柾夫会長(内外輸送社長)に業界の現状と課題を聞いた。(聞き手・石井麻里)
――JTTAの歩みについてお聞かせください
小幡 1970年に、関西地区の液体貨物を取り扱う企業数社が発起人となって会員を募り、翌71年に会員11社により、同業企業間の情報交換と親睦、法に関する対応と安全管理に関する研鑽を目的に「関西液体貨物業界」の名称で発足しました。その後、関東地区でも会が発足。93年に日本タンクターミナル協会(JTTA)と名称変更した後も、関東、関西の支部活動が中心でした。私が会長になった2003年から、本部制を導入し、支部活動を残しつつ活動を一本化しています。JTTA単独では、年4回の理事会、年1回の総会、例会(勉強会)や支部単位での勉強会、懇親会を通じて同業者との連携・コミュニケーション強化を図っており、日本危険物物流団体連絡協議会(大森寿明会長)にもメンバーとして参画しています。
――同業者との連携を重視されているのですね。
小幡 メーカーの海外移転が加速し、基礎化学品の生産は東南アジアにシフトしています。タンクターミナルが扱う液体バルク貨物に関しては、中間原料を日本に輸入する時代になり、川下に近い製品・半製品を小ロットで輸入するケースが増えてくることが予想されます。タンクターミナル各社は自社の特性、オリジナリティーを残しつつ、設備を時代のニーズに合わせていかなければなりません。ただ、タンクは設備投資額が大きいため、やみくもに設備を増やしたり、作り変えるわけにはいかず、自社で対応できないエリアや貨物については、同業者にアウトソーシングするなど協力体制が不可欠です。それには信頼関係が基本になければならず、こうした意味でもJTTAの活動を通じたコミュニケーションが重要となってきます。
――業界全体としての事業環境はいかがでしょうか。
小幡 メーカーの生産体制の再編や韓国や中国など近隣諸国のタンクターミナルとの競合の影響が考えられますが、将来を悲観することはないと思っています。まず、タンクターミナルにはほとんど新規参入がありません。物流の好立地にタンクターミナルに適した土地を取得するのは難しく、かつ施設を建てるにも消防法をはじめとする法規制に縛られるため、一から土地を取得して、タンクを建てる――というのでは事業の採算が合いません。結果として、既存の事業者に圧倒的に優位性があります。また、メーカーの生産の再編に伴い、自社生産から輸入に切り替えるケースがあちこちで出てきており、輸入あるいはそれを再び輸出する場合に、ストックポイントとしてのタンクターミナルのニーズは増えてくると思います。
――タンクのニーズも変化しつつあります。
小幡 荷主からはシビアな品質管理を要請されるようになり、従来、オーバースペックとされていたタンクの付帯設備がスタンダード化してきています。例えば、窒素シール、タンクの保温・遮熱設備などです。我々からすると設備投資が増えるのですが、ほとんどの場合に荷主に価格転嫁ができていません。安全・高品質なサービスに不可欠な設備投資については、将来的には、価格に反映されることが望ましいと思います。タンクターミナルの経営は、タンクの老朽化対策をはじめ長期的な設備投資への備えが必要で、次の世代だけでなく、次の次、さらにその次の世代まで見据え、地に足の付いた経営を行うことが求められます。
――安全対策のさらなる充実を図っていきます。
小幡 従来、タンクターミナルは船で入ってきたものをタンクに入れ、それを出荷する――という単純な作業がメインでした。タンクに付随する細かい作業が増えれば増えるほど、リスクが増大し、安全対策の強化が必要になってきます。最近、増えているのが、「一般取扱所」を活用したISOタンクコンテナやローリーからドラムへの詰め替えまたはその逆などを行うサービスです。各社が「マルチ~」などの名称で新しいサービスとして展開していますが、当社(内外輸送)では77年に新設した一般取扱所の中に設備を設け既にこのサービスを手掛けていました。実は、この液体を詰め替えるという作業は人手がかかり、飛散や被爆など最も危険を伴う作業なのです。
私が入社した当時は、保護具を身に付けると「男のくせに」などと先輩の社員に言われたものでした。しかし、冷静に考えると、危険に身をさらすことは何の自慢にもなりません。保護具を付けないで行った作業で負ったかぶれ傷は、30年以上経った今もうずきます。こうした自身の経験からも、安全に対して経営者がしっかり認識し、社員にそれを徹底させることがいかに大事かと痛感しています。輸入品の少量多品種化により、タンクターミナルでの各種詰め替え作業のニーズはこれから増えてくることが予想されますが、施設の整備だけでなく、作業内容と扱う貨物までも考えた素材の保護具の着用を徹底していくべきと考えています。
タンクターミナル各社が強みを生かした差別化戦略を展開
内外輸送は高圧ガスの取り扱いを強化
近年、タンクターミナルのトレンドの1つが多機能化だ。アルコールや化学品のタンク保管・輸送がメインの内外輸送(本社・横浜市鶴見区、小幡柾夫社長)では、横浜支店(横浜市鶴見区)の再整備で危険物倉庫、危険物・一般品の定温倉庫、多目的作業場などを新設し、業容拡大を図った。
内外輸送で力を入れているのが、高圧ガスの取扱い。昨年7月には、高圧ガス専用倉庫のスペースを拡張し、より幅広い種類のガスを扱うことができる「第一種貯蔵所」に格上げした。取扱可能な高圧ガスの種類を増やすとともに、大型ガスシリンダーにも対応できるよう3㌧フォークも導入している。
高圧ガス専用倉庫は保税貯蔵所の許可を得ており、入出庫、保管、流通加工、バンニング・デバンニングのほか、協力会社と連携して貨物のセキュアリング(固定)も行うなど一貫サービス体制を構築。高圧ガスは半導体などの製造に用いられ、輸出が増えているが、高圧ガスを扱う営業倉庫は少なく、内外輸送では事業の第3の柱に成長させたい考えだ。
(2012/6/28 カーゴニュース紙掲載)