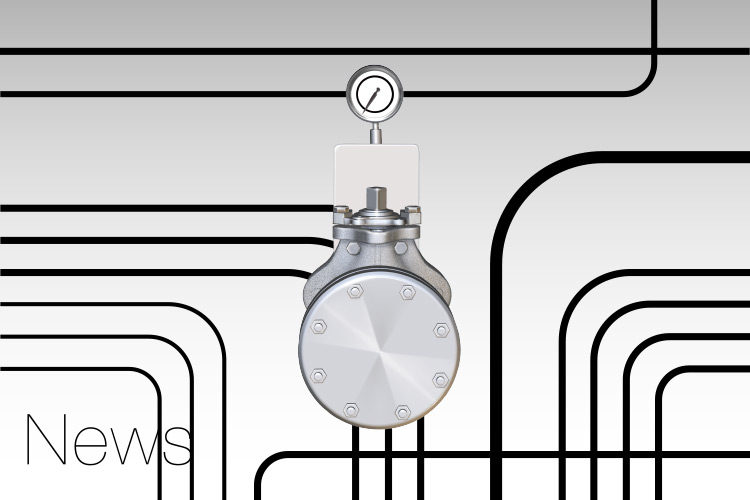日本タンクターミナル協会が消防庁から講師を招き例会を開催
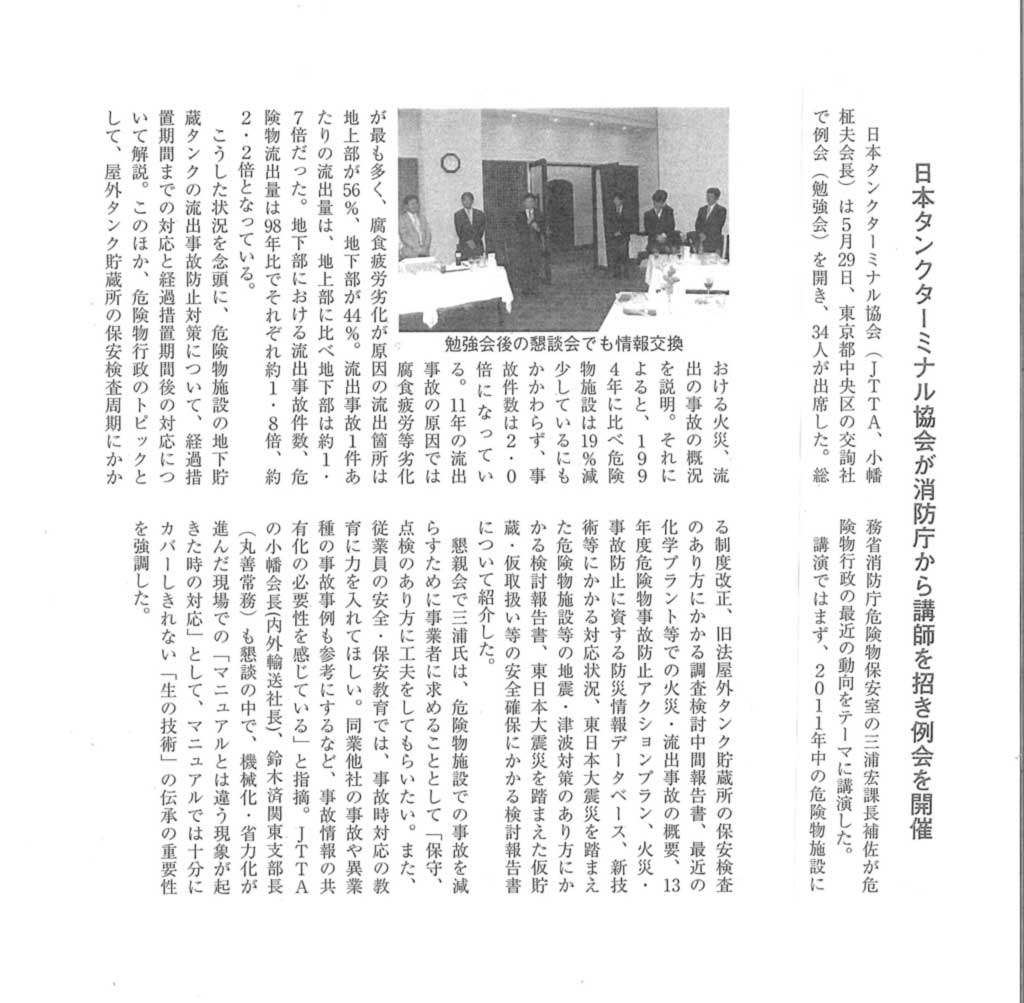
日本タンクターミナル協会(JTTA、小幡柾夫会長)は5月29日、東京都中央区の交詢社で例会(勉強会)を開き、34人が出席した。総務省消防庁危険物保安室の三浦宏課長補佐が危険物行政の最近の動向をテーマに講演した。
講演ではまず、2011年中の危険物施設における火災、流出の事故の概況を説明。それによると、1994年に比べ危険物施設は19%減少しているにもかかわらず、事故件数は2.0倍になっている。11年の流出事故の原因では腐食疲労等劣化が最も多く、腐食疲労劣化が原因の流出箇所は地上部が56%、地下部が44%。流出事故1件あたりの流出量は、地上部に比べ地下部は約1.7倍だった。地下部における流出事故件数、危険物流出量は98年比でそれぞれ約1.8倍、約2.2倍となっている。
こうした状況を念頭に、危険物施設の地下貯蔵タンクの流出事故防止対策について、経過措置期間までの対応と経過措置期間後の対応について解説。このほか、危険物行政のトピックとして、屋外タンク貯蔵所の保安検査周期にかかる制度改正、旧法屋外タンク貯蔵所の保安検査のあり方にかかる調査検討中間報告書、最近の化学プラント等での火災・流出事故の概要、13年度危険物事故防止アクションプラン、火災・事故防止に資する防災情報データベース、新技術等にかかる対応状況、東日本大震災を踏まえた危険物施設等の地震・津波対策のあり方にかかる検討報告書、東日本大震災を踏まえた仮貯蔵・仮取扱い等の安全確保にかかる検討報告書について紹介した。
懇親会で三浦氏は、危険物施設での事故を減らすために事業者に求めることとして「保守、点検のあり方に工夫をしてもらいたい。また、従業員の安全・保安教育では、事故時対応の教育に力を入れてほしい。同業他社の事故や異業種の事故事例も参考にするなど、事故情報の共有化の必要性を感じている」と指摘。JTTAの小幡会長(内外輸送社長)、鈴木済関東支部長(丸善常務)も懇談の中で、機械化・省力化が進んだ現場での「マニュアルとは違う現象が起きた時の対応」として、マニュアルでは十分にカバーしきれない「生の技術」の伝承の重要性を強調した。
(2013/6/6カーゴニュース紙掲載)
講演ではまず、2011年中の危険物施設における火災、流出の事故の概況を説明。それによると、1994年に比べ危険物施設は19%減少しているにもかかわらず、事故件数は2.0倍になっている。11年の流出事故の原因では腐食疲労等劣化が最も多く、腐食疲労劣化が原因の流出箇所は地上部が56%、地下部が44%。流出事故1件あたりの流出量は、地上部に比べ地下部は約1.7倍だった。地下部における流出事故件数、危険物流出量は98年比でそれぞれ約1.8倍、約2.2倍となっている。
こうした状況を念頭に、危険物施設の地下貯蔵タンクの流出事故防止対策について、経過措置期間までの対応と経過措置期間後の対応について解説。このほか、危険物行政のトピックとして、屋外タンク貯蔵所の保安検査周期にかかる制度改正、旧法屋外タンク貯蔵所の保安検査のあり方にかかる調査検討中間報告書、最近の化学プラント等での火災・流出事故の概要、13年度危険物事故防止アクションプラン、火災・事故防止に資する防災情報データベース、新技術等にかかる対応状況、東日本大震災を踏まえた危険物施設等の地震・津波対策のあり方にかかる検討報告書、東日本大震災を踏まえた仮貯蔵・仮取扱い等の安全確保にかかる検討報告書について紹介した。
懇親会で三浦氏は、危険物施設での事故を減らすために事業者に求めることとして「保守、点検のあり方に工夫をしてもらいたい。また、従業員の安全・保安教育では、事故時対応の教育に力を入れてほしい。同業他社の事故や異業種の事故事例も参考にするなど、事故情報の共有化の必要性を感じている」と指摘。JTTAの小幡会長(内外輸送社長)、鈴木済関東支部長(丸善常務)も懇談の中で、機械化・省力化が進んだ現場での「マニュアルとは違う現象が起きた時の対応」として、マニュアルでは十分にカバーしきれない「生の技術」の伝承の重要性を強調した。
(2013/6/6カーゴニュース紙掲載)