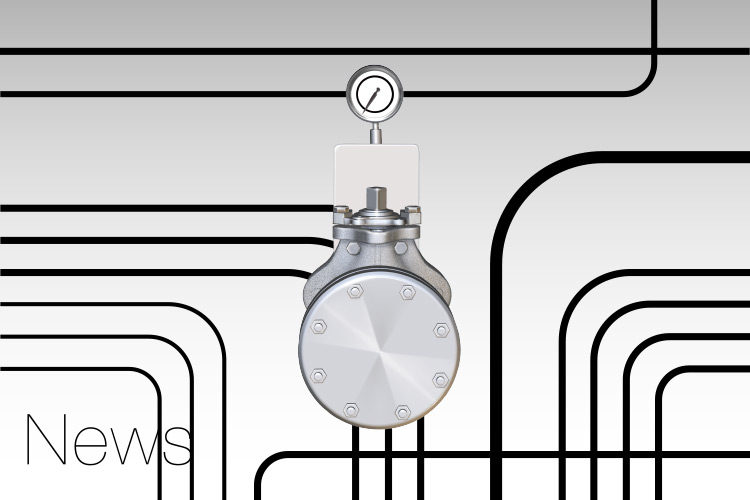日本タンクターミナル協会
日本アルコール産業鹿島工場、鹿島タンクターミナルで研修
最新鋭のアルコール工場、タンクターミナルを見学
2014.7.17.jpg)
日本タンクターミナル協会(JTTA、小幡柾夫会長)は10日、茨城県の鹿島地区で2014年度の研修会を開催し、関東支部、関西支部から34人が参加した。展望棟から鹿島港を見学した後、日本アルコール産業(本社・東京都中央区、岡留伸一郎社長)の鹿島工場、会員企業である鹿島タンクターミナル(本社・茨城県神栖市、野口三郎社長)を訪問し、施設の概要などについて説明を受けた。
最初に、鹿島灘を一望できる港公園の展望棟に上り、鹿島臨海工業地帯などの概要を学んだ。鹿島港は東京から80㌔㍍にあり、首都圏の新しい物流拠点として注目されるY字型の堀込港湾。高松地区(北部地区663㌶)に鉄鋼を中心とした工場群、神の池東部地区(東部地区734㌶)に石油精製、石油化学・火力発電所等、神の池西部地区(西部地区448㌶)に鉄鋼製品の二次加工その他の工業、波崎地区(274㌶)に化学工業その他の工場が立地。中央航路を挟んで高松地区には新日鐵住金鹿島製鉄所、東部地区には三菱化学鹿島事業所がある。2011年3月11日の東日本大震災では、港湾施設や周辺インフラが深刻な影響を受けたが、昨年4月には鹿島港外港公共ふ頭A岸壁が耐震強化岸壁として供用開始した。
続いて、日本アルコール産業鹿島工場を訪問。蒸留棟やタンク、ローリー出荷場、分析室などを見学した。同社では安定同位体比質量分析により、粗留アルコールの輸入段階でその由来原料農産物を自ら特定し、原材料のトレーサビリティを確保。製品化にあたっては、原料タンクから出荷に至るまで生産履歴を管理。タンカー積み込み時のサンプルを一足早く空輸し、日本到着時の積荷を再チェックするという厳しい管理を行っている。発酵アルコールを製造する鹿島工場は2001年7月に操業を開始した最新鋭の工場で、原料の船受け入れができるため原料調達力が強化され、製品の船払い出しは物流の効率化と安定供給に貢献している。
最後に、丸全昭和運輸グループの鹿島タンクターミナルを見学。同ターミナルは12年10月に業務を開始。バース延長は170㍍、水深9.3㍍で、最大載貨重量トンは1万5000DWT、最大接岸船の全長は154㍍となっている。屋外タンク10基(指定可燃物タンクは600㌔㍑1基と990㌔㍑2基、危険物タンクは600㌔㍑2基、750㌔㍑1基、990㌔㍑4基)を配備。危険物屋内貯蔵所(594平方㍍)、ローリー充てん所(6レーン)、ドラム充てん機、トラックスケール(50㌧)、泡モニター、監視システムなどを備える。タンクと危険物屋内貯蔵所はともに保税。同ターミナルの敷地を活用したISOタンクコンテナの保管作業も始めており、リーチスタッカーを導入。ISOタンクコンテナの加温(温水・蒸気)にも対応する。
今回訪問した日本アルコール産業鹿島工場は広大な敷地面積で増設の余地があり、鹿島タンクターミナルも将来増設予定地があった。また、両施設のタンクは1977年に改定された耐震設計基準施行以降に建設された、いわゆる「新法タンク」で、タンク間の距離が長いことが特徴的で、これらを実際に見られる、会員にとって充実した研修会となった。
(2014/7/17カーゴニュース紙掲載)