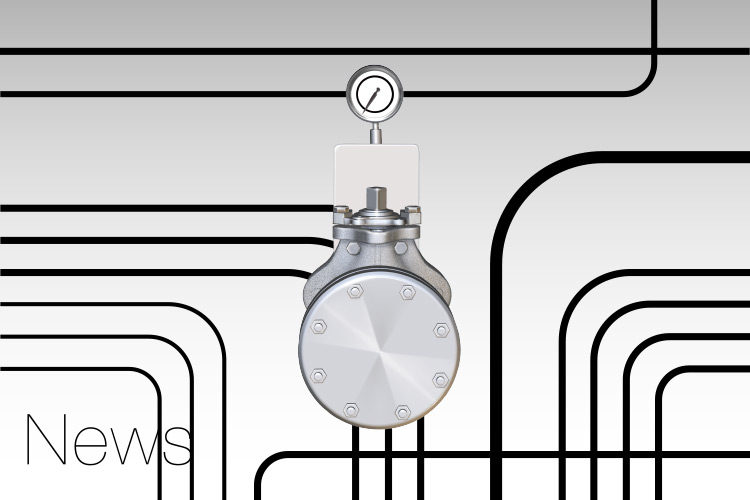日本タンクターミナル協会
例会で消防庁危険物保安室の鳥枝課長補佐が講演
危険物行政の動向、地震・津波対策学ぶ

日本タンクターミナル協会(JTTA、小幡柾夫会長)は9日、東京都中央区の交詢社で例会(勉強会)を開き、関東支部、関西支部から43人が出席した。消防庁危険物保安室の鳥枝浩彰課長補佐が、昨今の危険物行政の動向、東日本大震災を踏まえた危険物施設の地震・津波対策について講演した。
鳥枝氏は、危険物施設の数は減少しているが、危険物施設における事故は増えている状況を報告。ただ、「重大かそうではない事故かについては分析されておらず、軽微な事故が増えている可能性もあり、事故分析の仕方を見直そうとしている」と説明。事故としての報告件数が増えた背景として、企業のコンプライアンス強化を指摘した。
火災事故発生原因では人的要因、流出事故発生原因は腐食疲労劣化など物的要因によるものが多い。防止策として、①安全に関する技術の伝承・人材育成②設備等の安全を向上させる取り組み③安全対策を確実に実施するための体制づくり④地震・津波対策の推進――を挙げ、「体制づくりが肝になる。施設の設計部門と連用部門の連携が重要」と述べた。
近年の危険物施設の事故事例を紹介し、「know how(どうやるか)は知っていても、なぜやるか、know whyは知らないことがある」とし、マニュアルなどの背景にある原理原則の理解の必要性を指摘。
「危険物の火災は一瞬で盛期火災になるため危険が大きい。知識や経験でそれを理解することが課題」と強調。事故情報を共有する行政側の取り組みとして、消防庁、厚生労働省、経済産業省の「石油コンビナート等における災害防止対策検討関係省庁連絡会議報告書」に基づく3省共同運営サイトを紹介した。
最近の危険物行政に対する要望への対応では、消防法危険物における「海上コンテナ仮貯蔵所(包括承認)制度」の新設についての対応を説明。「安全対策の不備が出てこないように、消防が承認する制度は維持し、できるだけ港の近隣の消防で受け付けるようにし、提出書類を少なくする」との考え方を説明した。
また、屋外タンク貯蔵所の新基準適合確認状況について、「今後新基準適合期限を迎える小さなクラスのタンクについても計画的かつ早期に新基準への適合確認を進めていくことが重要」で強調。「屋外タンク貯蔵所に関する耐震安全性確認のための調査検討会」にも触れ、特定タンクが検討対象で、準特定タンクについては未定とした。
(2015/4/16 カーゴニュース紙掲載)