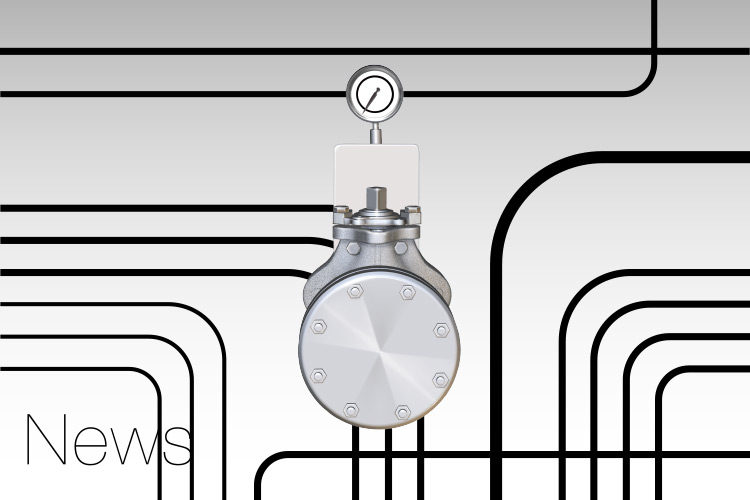日本タンクターミナル協会が勉強会
非定常時の安全管理 課題

業界一丸となって災害ゼロを目指している日本タンクターミナル協会(JTTA、会長・小幡柾夫内外輸送社長)はこのほど、恒例となっている勉強会を開催した。講演した総務省消防庁危険物保安室の鈴木建志課長補佐は、通常作業以外の現場で発生した重大事故などを踏まえ、非定常作業などに対応したリスクアセスメントの重要性などを解説。危険物の安全管理を実践するうえで求められる対策を提示した。
ここ20年間の危険物施設における火災、流出事故の総件数をみると、1994年の287件から14年には599件と2倍超に増加。一方で危険物施設数は約56万件から約42万5000件へと2割程度減少した。1万施設当たりでは5件から14件と発生確率が上昇。ただ、人的被害や被害額ほぼ横ばいであるため、軽微な事故が増えているという側面もある。
発生原因は、14年の統計では火災原因の6割超が人的要因。このうち静電気火花が約21%と最も多く、高温表面熱が約16%、加熱着火が約11%と続いている。
一方、流出事故では6割強を物的要因が占める。腐食疲労など劣化による流出が多く、こうした物的要因は09年以降増加傾向にあるが、対照的に人的要因は減少している。鈴木課長補佐は「国内には設置から40~50年が経過している地下タンクが3800基あり、20年以上に範囲を広げると総数は3万4000基に上る」と背景を指摘。ただ、10年の法令改正を経て「内面ライニングや電気防食の対策が採られ、軽微な流出事故は減ってきている」という。
事故件数が増加するなか、重大事故の事例を通してリスクアセスメントの内容・程度が不十分な点や人材育成・技術伝承が進んでいない点、過去の事故を含めた情報共有・伝達の不足などが原因・背景の共通点としてみえてくる。
事業者や業界団体が取り組むべき対策として、非定常作業時や緊急時を想定したリスクアセスメントに加え、設備・運転方法の変更があった際や2~3年置きの保守作業などでも対応をまとめる必要性を強調。「アセスメントを作っても守られないと意味がない。策定する安全管理部門と実際に作業する運用部門との連携も大切」と話した。
行政側の取り組みでは、02年から開催している危険物等事故防止対策情報連絡会の機能強化が進む。16年度からは人的要因に起因する事故の低減を目指し、人間工学の専門家を委員に追加する。事故防止対策の目標を重大事故の発生防止としたうえで、業界団体には所管業界の実態に即した対策を推進してもらい、軽微な事故の防止も促す。また、消防庁は都道府県別の事故発生状況を公表する。
講演の最後には消防庁の16年度の検討事項に挙がっているトピックスを紹介。このうち、政府の国土強靭化計画に加え、東京五輪にもかかわる非常用電源設備の導入については、12年のロンドン五輪では非常用発電機が600台準備され、燃料となる重油も大量になったことから、貯蔵・取り扱い方法の多様化や電力供給の一部を水素エネルギーで賄うプロジェクトに関する対応を検討していることを解説した。
(2016/4/13 化学工業日報 掲載)
ここ20年間の危険物施設における火災、流出事故の総件数をみると、1994年の287件から14年には599件と2倍超に増加。一方で危険物施設数は約56万件から約42万5000件へと2割程度減少した。1万施設当たりでは5件から14件と発生確率が上昇。ただ、人的被害や被害額ほぼ横ばいであるため、軽微な事故が増えているという側面もある。
発生原因は、14年の統計では火災原因の6割超が人的要因。このうち静電気火花が約21%と最も多く、高温表面熱が約16%、加熱着火が約11%と続いている。
一方、流出事故では6割強を物的要因が占める。腐食疲労など劣化による流出が多く、こうした物的要因は09年以降増加傾向にあるが、対照的に人的要因は減少している。鈴木課長補佐は「国内には設置から40~50年が経過している地下タンクが3800基あり、20年以上に範囲を広げると総数は3万4000基に上る」と背景を指摘。ただ、10年の法令改正を経て「内面ライニングや電気防食の対策が採られ、軽微な流出事故は減ってきている」という。
事故件数が増加するなか、重大事故の事例を通してリスクアセスメントの内容・程度が不十分な点や人材育成・技術伝承が進んでいない点、過去の事故を含めた情報共有・伝達の不足などが原因・背景の共通点としてみえてくる。
事業者や業界団体が取り組むべき対策として、非定常作業時や緊急時を想定したリスクアセスメントに加え、設備・運転方法の変更があった際や2~3年置きの保守作業などでも対応をまとめる必要性を強調。「アセスメントを作っても守られないと意味がない。策定する安全管理部門と実際に作業する運用部門との連携も大切」と話した。
行政側の取り組みでは、02年から開催している危険物等事故防止対策情報連絡会の機能強化が進む。16年度からは人的要因に起因する事故の低減を目指し、人間工学の専門家を委員に追加する。事故防止対策の目標を重大事故の発生防止としたうえで、業界団体には所管業界の実態に即した対策を推進してもらい、軽微な事故の防止も促す。また、消防庁は都道府県別の事故発生状況を公表する。
講演の最後には消防庁の16年度の検討事項に挙がっているトピックスを紹介。このうち、政府の国土強靭化計画に加え、東京五輪にもかかわる非常用電源設備の導入については、12年のロンドン五輪では非常用発電機が600台準備され、燃料となる重油も大量になったことから、貯蔵・取り扱い方法の多様化や電力供給の一部を水素エネルギーで賄うプロジェクトに関する対応を検討していることを解説した。
(2016/4/13 化学工業日報 掲載)