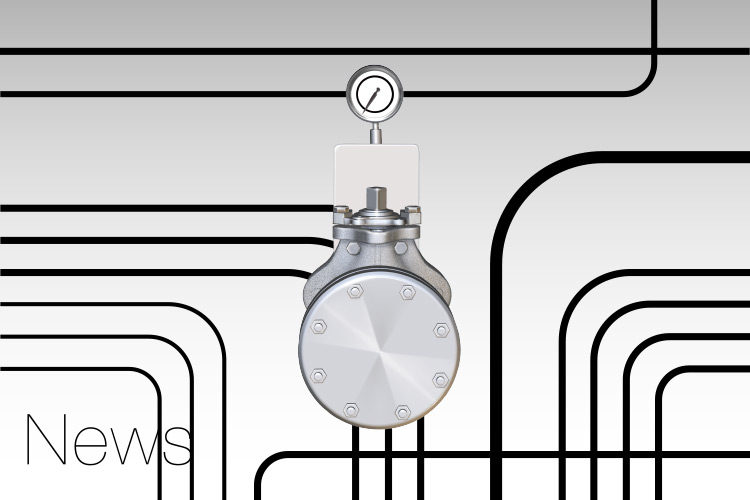JTTA「昨今の危険物行政の動向について」をテーマに勉強会
消防庁危険物保安室の鈴木課長補佐が講演

日本タンクターミナル協会(JTTA、小幡柾夫会長)は7日、東京都内で例会(勉強会)を開き、関東支部、関西支部から計45人が出席した。総務省消防庁危険物保安室の鈴木建志課長補佐が、「昨今の危険物行政の動向について」と題して講演した。
講演によると、2014年中の事故件数は599件、危険物施設数は42万6364件で最も事故件数が少なかった1994年に比べ、事故件数は約2倍に増加し、施設数は約2割減少。一方で被害にはあまり差がなく、鈴木氏は「軽微な被害の事故が増えている。また、世の中全体の施設で火災件数は減っているが、危険物施設に限定すると増えている」と指摘した。危険物火災・流出事故の原因の推移をみると、「火災については人的要因が多く、流出では09年以降、物的要因が右肩上がりに増えている」と説明した。
近年の主な危険物に係る事故およびその対応、15年度に発生した屋外タンク貯蔵所の事故事例について紹介。危険物等に係る事故防止対策の推進では14年5月に、危険物等事故防止懇談会による危険物等事故防止安全憲章、石油コンビナート等における災害防止対策検討関係省庁連絡会議の報告書を取りまとめ、地震・津波対策も盛り込んだ「危険物事故防止アクションプラン」を策定。同報告書に基づき、総務省消防庁、厚生労働省、経済産業省の3省共同運営サイトも設置した。
なお、同報告書では、最近の重大事故の原因・背景に係る共通点として、①リスクアセスメントの内容・程度が不十分②人材育成・技術伝承が不十分③情報共有・伝達の不足や安全への取り組みが形骸化――を指摘。事業者が取り組むべき事項では「自主保安向上に向けた安全確保体制の整備と実施」「リスクアセスメントの徹底」「人材育成の徹底」「社内外の知見の活用」を、業界団体が取り組むべき事項では、事故情報(教訓)・安全対策の共有、教育訓練の実施、安全意識の向上に向けた取り組みを挙げた。
「危険物事故防止に関する基本方針」に基づき取り組みを継続してきたが、現状では掲げられた目標(事故の件数および被害を94年頃のレベル以下に減らす)は達成できていないことから、16年度から、危険物等事故防止対策情報連絡会の委員に人間工学の専門家を追加。「危険物等に係る重大事故の発生を防止すること」を目標とし、関係業界団体は所管する業界等の業態・実態に応じた事故防止対策を推進。重大事故が発生していない場合でも、軽微な事故の発生を防止する方策を検討する。
また、94年~15年の軽微な火災および流出事故の詳細分析、14、15年に重大事故が発生した事業所への聞き取り調査の結果を踏まえ、「ヒューマンエラーが発生しても重大事故を発生させない『フェイルセーフ』を志向した対策」「危険物施設における危険物以外の火災の防止策」「作業方法の変更があった場合のリスクアセスメント」「一般取扱所における設備の老朽化対策、従業員への作業手順の指示の徹底」を危険物に係る事故防止に向けて提案している。
(2016/4/14 カーゴニュース 掲載)
講演によると、2014年中の事故件数は599件、危険物施設数は42万6364件で最も事故件数が少なかった1994年に比べ、事故件数は約2倍に増加し、施設数は約2割減少。一方で被害にはあまり差がなく、鈴木氏は「軽微な被害の事故が増えている。また、世の中全体の施設で火災件数は減っているが、危険物施設に限定すると増えている」と指摘した。危険物火災・流出事故の原因の推移をみると、「火災については人的要因が多く、流出では09年以降、物的要因が右肩上がりに増えている」と説明した。
近年の主な危険物に係る事故およびその対応、15年度に発生した屋外タンク貯蔵所の事故事例について紹介。危険物等に係る事故防止対策の推進では14年5月に、危険物等事故防止懇談会による危険物等事故防止安全憲章、石油コンビナート等における災害防止対策検討関係省庁連絡会議の報告書を取りまとめ、地震・津波対策も盛り込んだ「危険物事故防止アクションプラン」を策定。同報告書に基づき、総務省消防庁、厚生労働省、経済産業省の3省共同運営サイトも設置した。
なお、同報告書では、最近の重大事故の原因・背景に係る共通点として、①リスクアセスメントの内容・程度が不十分②人材育成・技術伝承が不十分③情報共有・伝達の不足や安全への取り組みが形骸化――を指摘。事業者が取り組むべき事項では「自主保安向上に向けた安全確保体制の整備と実施」「リスクアセスメントの徹底」「人材育成の徹底」「社内外の知見の活用」を、業界団体が取り組むべき事項では、事故情報(教訓)・安全対策の共有、教育訓練の実施、安全意識の向上に向けた取り組みを挙げた。
「危険物事故防止に関する基本方針」に基づき取り組みを継続してきたが、現状では掲げられた目標(事故の件数および被害を94年頃のレベル以下に減らす)は達成できていないことから、16年度から、危険物等事故防止対策情報連絡会の委員に人間工学の専門家を追加。「危険物等に係る重大事故の発生を防止すること」を目標とし、関係業界団体は所管する業界等の業態・実態に応じた事故防止対策を推進。重大事故が発生していない場合でも、軽微な事故の発生を防止する方策を検討する。
また、94年~15年の軽微な火災および流出事故の詳細分析、14、15年に重大事故が発生した事業所への聞き取り調査の結果を踏まえ、「ヒューマンエラーが発生しても重大事故を発生させない『フェイルセーフ』を志向した対策」「危険物施設における危険物以外の火災の防止策」「作業方法の変更があった場合のリスクアセスメント」「一般取扱所における設備の老朽化対策、従業員への作業手順の指示の徹底」を危険物に係る事故防止に向けて提案している。
(2016/4/14 カーゴニュース 掲載)