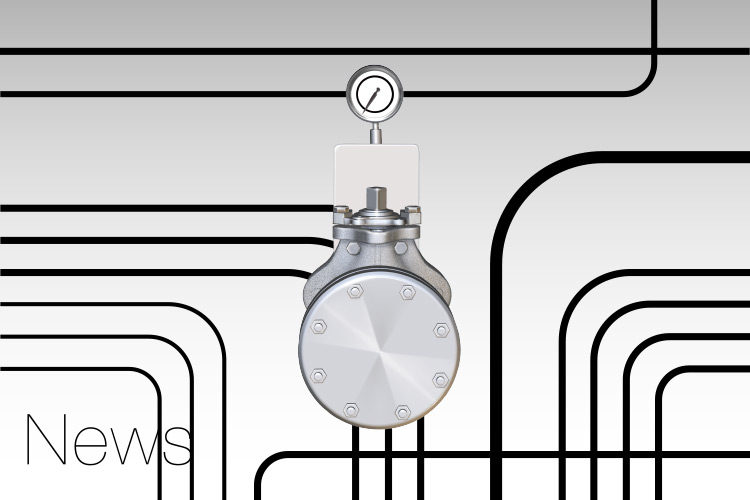JTTA
例会で消防庁危険物保安室の竹本課長補佐が講演
重大事故の原因・背景の共通点や危険物行政の動向学ぶ

日本タンクターミナル協会(JTTA、小幡柾夫会長)は13日、例会(勉強会)を開催し、関東支部、関西支部から計42人が出席した。消防庁危険物保安室の竹本吉利課長補佐が昨今の危険物行政の動向について講演。竹本氏は「事故防止のメインプレイヤーは各事業所」と強調し、最近の重大事故の原因・背景にかかる共通点として①リスクアセスメントの内容・程度が不十分②人材育成・技術伝承が不十分③情報共有・伝達の不足や安全への取り組みが形骸化――を挙げた。
2015年中の危険物施設における事故件数は580件で前年より19件減少したが、最も事故件数が少なかった1994年に比べ約2倍。一方で94年から危険物施設数は約4分の3に減少している。火災事故(215件)の発生原因では、維持管理や操作にあたっての不手際など「人的要因」によるものが多く、流出事故(365件)では物的要因によるものが多くを占め、とくに「腐食等劣化」が全体の約66.5%と目立つ。
近年、化学メーカー工場で起きた危険物等にかかる主な事故を紹介し、共通点として「想定していない手順の不手際や、通常とは異なる条件での操作で化学品の重反応が加速し、爆発する事故が立て続けに起きた。これらはリスク管理や細部を確認することにより防ぐことは可能」と指摘。通常時と異なる作業を行う際にリスク点検の必要性を強調した。
事故が起きた際、「まずは自分たちだけで対応しようとし、消防機関への通報が遅れる例が散見される。想定よりも消火時間がかかり、事業所の被害が拡大してしまう。役割分担し、事故が起きたら直ちに消防機関に通報し、駆け付けた消防と一緒に安全な消防活動を行うことで早期に鎮火し、事業所被害の軽減につながる」とし、アドバイザー的立場にある消防機関の情報・知見の活用を呼び掛けた。
消防庁では、02年に危険物等事故防止対策情報連絡会を発足。03年度には「危険物事故防止に関する基本方針」を策定し、「事故件数および被害を1994年頃のレベル以下に下げる」という目標を設定。毎年度「危険物事故防止アクションプラン」を策定し、関係者で取り組みを実施してきたが、最近の事故が増加傾向で、目標達成できておらず、軽微なものから重大なものまで事故を同じ1件として数えていた。
そこで同基本方針を廃止し、昨年3月にヒューマンエラーに起因する事故を低減するため、連絡会のメンバーとして人間工学・失敗学・心理学の専門家を追加。「危険物等にかかる重大事故の発生を防止すること」を新たな目標として設定。危険物施設における火災・流出事故にかかる「深刻度評価指標」を用いた統計分析により、深刻度が最も高いレベルとなる事故を「重大事故」として今年度中に分析する。
懇談会では、関谷和孝関東支部長(東京油槽)が講演を振り返り、「危険物の事故事例を心、頭に入れて事故のないタンクターミナルをめざそう」と挨拶。懇談会では危険物物流のトピックスについて情報交換が積極的に行われた。土井政之理事(アスト)が閉会の挨拶を担当し、「この会がますます発展してきているのは小幡会長(内外輸送)のおかげ。これからも発展していきたい」と述べた。
(2017/4/20 カーゴニュース 掲載)