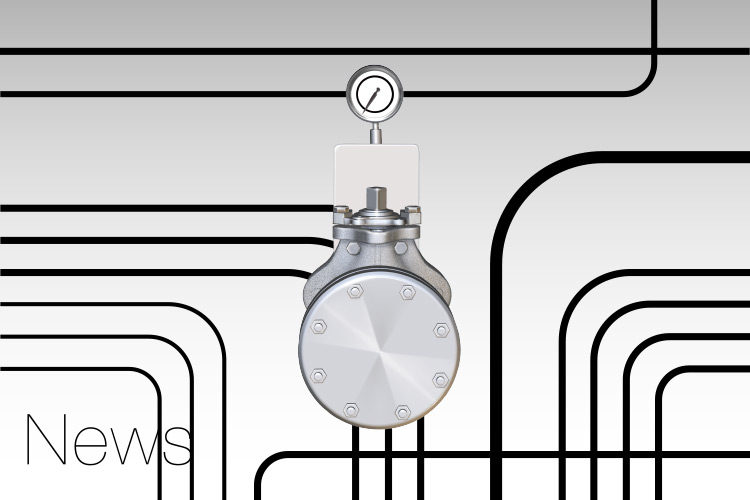危険物行政で消防庁講演
日本タンクターミナル協会主催
「重大事故」ゼロめざす

日本タンクターミナル協会(JTTA、会長・小幡柾夫内外輸送社長)はこのほど、国際文化会館(東京都港区)で恒例の勉強会を開催した。「昨今の危険物行政の動向について」をテーマに講演した総務省消防庁危険物保安室の竹本吉利課長補佐は、危険物にかかわる事故事例などを挙げながら具体的な安全・防止対策を解説。想定されるリスクに対する情報共有や事故状況の速やかな開示・把握などの重要性を指摘するとともに、危険物を扱う事業所と消防とのさらなる連携強化が必要との認識を示し、災害低減に向けた安全管理対策の徹底を呼びかけた。
危険物施設における事故原因をみると、火災は維持管理や操作の不手際など人的要因が多数を占める一方、流出事故は腐食疲労など経年劣化による物的要因が約6割以上となっている。
こうした状況に対し消防庁では、異常への監視方法や判断指標、異常発生時における緊急停止作業など必要な応急対応手順の周知徹底を廃油施設などに要請。化学工場などは点検・保守作業にともなう圧力・温度変化や洗浄剤使用時による火災危険性の有無確認などの徹底を求めている。
新たな事故防止対策としては、危険物などにかかる「重大事故」の発生防止を目標に設定。火災・流出事故にかかる「深刻度評価指標」を用いた統計分析により、深刻度が最も高いレベルとなる事故の発生防止に取り組んでいる。2016年度からは「危険物等事故防止対策実施要領」として実施事項を毎年度取りまとめるとし、竹本課長補佐は「こうした取り組みによって、まず重大事故の発生ゼロを目指したい」とした。
16年度の同実施要領によると、保安教育の充実による人材育成・技術の伝承、想定されるすべてのリスクに対する適時・適切な取り組み、第三者の客観的な評価など企業による体制作り、地震・津波対策の再検証と実施を主な対策として掲げている。危険物関連施設などにおける自動制御化の進展や業務の細分化・専門化にともない事故やトラブル経験が減少しており、現場の危険予測・対応能力の弱体化につながるリスクが高まっていることを踏まえ、「安全にかかる技術の伝承や人材育成はこれまで以上に重要事項となっている」と指摘した。
重大事故の原因・背景に関する共通点としては、リスクアセスメントの内容不十分、情報共有・伝達の不足や安全への取り組み形骸化などが挙げられた。日本企業は「責任感の強さなどから自己で処理しようとする傾向があるものの、通報の早期化や事故情報・状況の速やかな開示など事業所と消防のさらなる連携強化が結果的に被害の拡大を防ぐ」との認識を示した。
(2017/5/2化学工業日報 掲載)