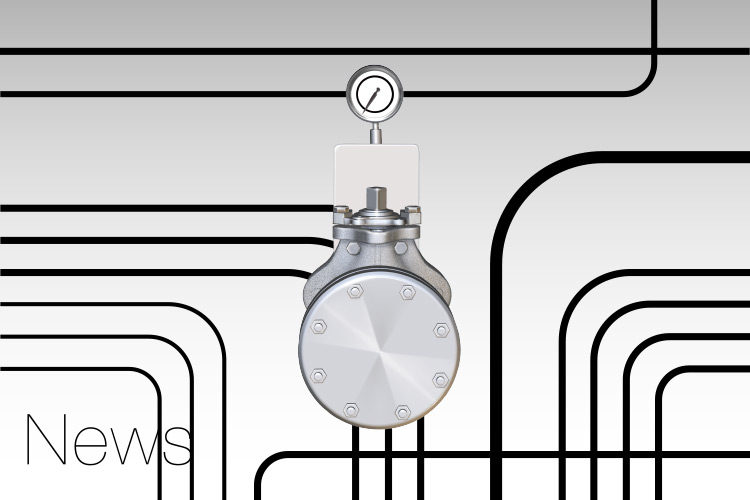危険物を扱う毎日が「初心」「原点」
常にスイッチが入る状態に
日本タンクターミナル協会会長 小幡 柾夫 氏

液体危険物を大量に保管するタンクターミナル 。物流業界の中では“装置産業”的な要素が強い業種だが、一方で、省力化・機械化のハードルが高く、ヒューマンエラーのリスクの大きさなど“人”の占める割合も大きい。日本タンクターミナル協会(JTTA)の小幡柾夫会長に業界の概況や人材育成について聞いた。
(インタビュアー/石井麻理)
タンクターミナル業界では、最近は活発な設備投資やM&Aの動きも見られるようになりました。
小幡 業界全体としてタンクはタイトです。タンクターミナルはその事業用地が希少なこともあって、新規参入のハードルが高く、どちらかというと需要が供給を上回る状況が続いていました。ここへ来て、既存の事業者が燃料系のタンクを買収するケースも見られ、タンクの供給が少しずつ増えてきています。今後もこうしたM&Aは想定され、将来的に内需が縮小した時に供給過多となる懸念もあります。
仮にそうなっても、価格競争ではなく、サービス品質で競う方向に意識を向けなければなりません。業界全体として安全・品質への意識は高く、いまでもサービス品質は優劣つけがたいかもしれませんが、それでも品質レベルを上げるためにやれることはまだたくさんあると思っています。
物流業界全体として労働力不足が深刻化していますが、タンクターミナルではどうですか。
小幡 まず、一般論として若い人の仕事に対する価値観が変わってきています。「転勤したくない」「残業はしたくない」など、ライフスタイルが仕事中心からプライベート中心に変わってきています。そういう中で、タンクターミナル業界の給与水準は他の業種と比べて悪くなく、また、夜間の作業がありません。残業が少なく、家族との時間を大事にできますので社員の定着率がよく、他の業界から転職してくる人もいます。物流業界と一括りにはできず、タンクターミナルは今の若い人が理想とする仕事の条件に近いのではないかと感じます。
そうすると、トラックや倉庫のように「働き方改革」への対応で頭が痛い なんてことはないのですね。
小幡 時間外労働が少ないという意味では、ほぼ対応はできていると思います。ただ、個人的には「寝食を忘れて仕事に打ち込む」という経験があってもいいのではないかと思うのです。もちろん、ずっとそれが続くようではいけませんが…。また、社員教育をしっかりやろうとすると業務時間内にはできず、どうしても業務終了後の「時間外」になってしまいます。「残業や長時間労働はいけません」といういまの風潮で、「早く仕事を覚えたい」「仕事ができるようになりたい」という志までなくされては困ります。
今後も人が関与する部分が相当残る
「働き方改革は」は、一方では仕事の生産性を高めようという狙いもあります。タンクターミナル事業の機械化・省力化についてはどう考えますか。
小幡 2016年に危険部施設で起きた火災事故の5割弱が人的要因ということです。ヒューマンエラーを未然に防ぐためにAI活用の可能性があるのか検討していく必要もあります。ただ、同じ危険物でもガソリンなど燃料は品種が限られているため機械化しやすいのですが、ケミカルは種類が様々で、物性、比重、粘度も異なります。とりわけ、パブリックタンク(営業用タンク)の場合、タンクに入れる製品が都度変わりますので、機械化が難しく、今後も人が関与する部分が相当残るだろうと考えています。だからこそ社員教育が重要です。
では機械化に頼らず、ヒューマンエラーをどう防いでいくのでしょう。これはタンクターミナルに限らず、物流会社にとって永遠の課題だと思いますが…。
小幡 作業のミスをする人の原因を辿ると、その人の性格的なところにも原因があります。性格を見極め、場合によってはリスクの少ない仕事に従事してもらうことも必要でしょう。タンクターミナルは大量の危険物を保管し、かつ人が関与する部分が大きいだけに、「手遅れ」になっては困るわけです。人員配置について「適材適所」と言われますが、現実的にはそれほど選択の余地はありません。だからこそ、採用の段階で履歴書ひとつをとっても、書き方であるとか証明写真の貼り方など何らかの“シグナル”を感知することが重要になります。
絶対に緩めてはならないポイントを押さえる
そういったリスク管理も社会的責任ということですね。普段の仕事ではどういう点に注意したらいいと思いますか。
小幡 人材育成に関しては、長所を伸ばし、短所は会社、すなわち教育する側が補い、プラスに持っていく努力をすべきです。例えば、作業ミスや事故を防止するため、作業員本人が行っている実際の作業風景を録画し、その画像を教育に活用することも有効な手段だと思います。「模範ビデオ」を見せても意味がなく、本人の画像だからこそ「ミスや事故につながりやすいのはどういう作業のやり方か」理解できるのです。
人は集中した状態がずっと続くものではなく、締めるところ、緩めるところのメリハリが必要です。仕事においても絶対に緩めてはならないポイントを押さえること 。これが一番大事だと思います。昨年は大企業の不祥事が報じられましたが、その都度、「原点に戻る」「初心に戻る」と言われます。しかし、危険物を扱う我々の仕事は、毎日が「原点」「初心」でなければなりません。重要なのは、作業を始める時に常にスイッチが入る状態にしておくことです。
(2018/5/29 カーゴニュース 掲載)